LLMOとは?生成AI時代に必要なSEO対策とWeb担当者の実践ポイント

ChatGPTやGoogleのAI Overviewの登場により、検索のあり方は劇的に変化してきました。企業のWeb担当者にとっては、「これまでのSEO施策は無駄にならないのか?」「これから何をすべきなのか?」といった不安はあると思います。
この記事では、2023~2024年頃からSEO業界で重要なテーマとなっているLLMO(Large Language Model Optimization)に着目し、企業のWeb担当者が今考えるべきポイントを整理してみました。
LLMOはなぜ注目されているのか?
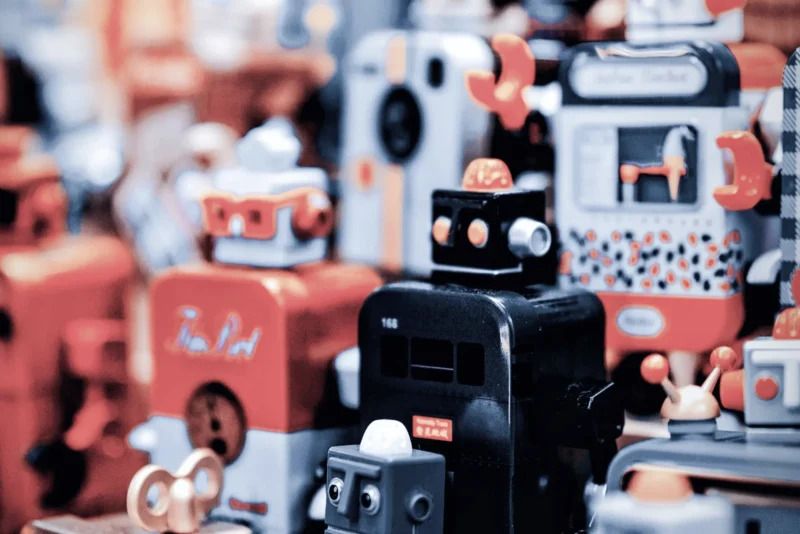
2022年末のChatGPTが公開され、ユーザーの検索行動は大きく変わりました。
これまでユーザーは検索エンジンにキーワードを入力し、リンクをクリックして情報を探していましたが、現在ではAIに直接質問を投げかけ、その場で回答を得る、いわゆる「ゼロクリックサーチ」が急速に広がっています。
さらに、GoogleのAI Overviewは、検索結果の最上部に大きく表示されるため、従来の検索上位コンテンツであってもクリックされにくくなりました。検索体験が1ページ目で完結する機会も増え、従来の「上位表示=流入増」という単純な構図が崩れつつあります。
つまり、今までのSEO対策のように「とにかく上位を狙う」施策では不十分になりつつあるのです。
ChatGPTが急速に普及したように、GoogleのAI Overview、さらには今後導入が予告されているAI Modeへの対応も、無視できない状況に入っています。
これまで企業のWeb担当者は「SEO」を意識してコンテンツや導線を整備してきましたが、これからは「AIが正しく理解・引用できる情報」を整備する視点が欠かせません。
そのための新しいアプローチが、LLMO(Large Language Model Optimization)であり、SEO対策の延長線上にある重要テーマの一つとなっています。
LLMOが注目され始めた時期

LLMOという概念は、突然生まれたものではなく、検索環境の変化とともに徐々に注目されるようになりました。時系列で振り返ると、その背景が見えてきます。
2023年初頭
SEO業界で「検索からAIへのシフト」が語られ始めます。ChatGPTの普及により「ユーザーが検索せずにAIに直接聞く」という行動が増加し始めました。
2023年中盤
米国のSEOカンファレンスにおいて「AI最適化」「Generative Engine Optimization(GEO)」などの新しい概念が登場し始め、AIを前提としたコンテンツ最適化の重要性が議論され始めました。
2023年末~2024年
SEO対策の延長線上にある新しい取り組みとして、SEO関係者が「LLMO(Large Language Model Optimization)」という言葉を積極的に使い始めました。様々な言葉が生まれましたが、現時点ではLLMOというキーワードが主流なようで、和製英語だともいわれています。
2025年
Googleが「SGE(Search Generative Experience)」を導入し、検索体験にAI回答が組み込まれました。さらにChatGPTのブラウジング機能の普及により、「AIに引用されるかどうか」が企業のSEO戦略に直結するテーマとして定着してきています。
LLMO時代に求められるWeb担当者の視点

従来のSEO対策は「検索順位を上げ、クリック数を増やす」ことがゴールでした。
しかし、LLM(大規模言語モデル)の普及により、これからの課題は「検索結果やAIの回答に自社サイトがどう引用されるか」にシフトしています。
変化のポイント
- 従来SEO:検索順位の最適化(上位に表示されることが目的)
- LLMO:AI最適化(AIが正しく理解・引用できる情報を整備することが目的)
つまり、Web担当者は「順位」ではなく「引用」を意識した情報設計が必要になっています。
この視点の変化こそが、LLMO時代に求められる大きな転換点といえるでしょう。近年、LLMOについての記事は爆発的書かれていますが、ここで、頻出用語について解説していきます。
LLMO関連の専門用語の解説
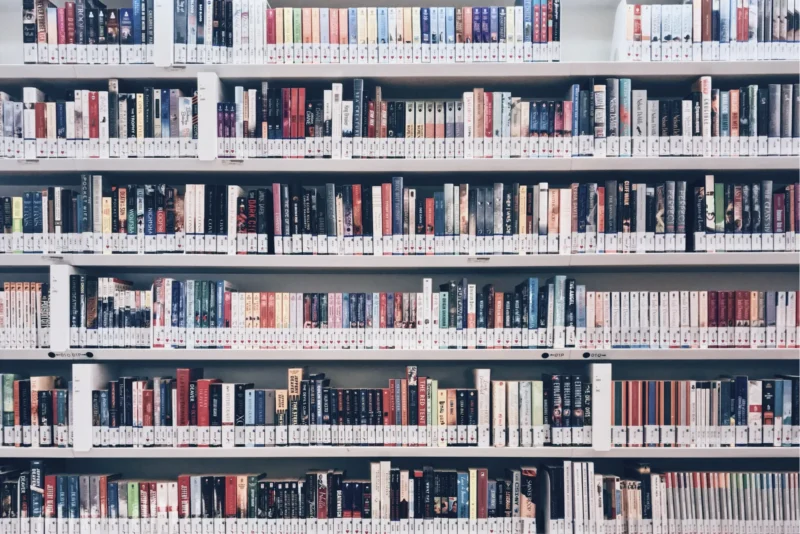
LLM(大規模言語モデル)
ChatGPTをはじめとするAIの基盤となる仕組みです。大量のテキストデータを学習し、人間の言葉に近い自然な文章を生成できます。
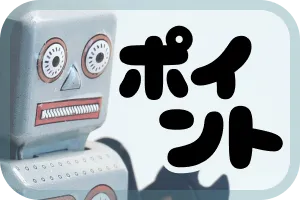 |
自社コンテンツがこの学習や回答生成にどう影響するかを意識する必要があります。 |
LLMO(Large Language Model Optimization)
AIが正しく理解し、回答に引用できるようWeb情報を最適化する取り組みです。従来の「検索エンジン最適化(SEO)」をAI時代に拡張した考え方ともいえます。
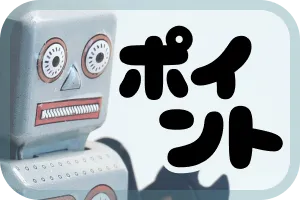 |
検索順位だけでなく「AIに引用されるかどうか」を視野に入れた情報設計が求められます。 |
ゼロクリックサーチ
ユーザーがリンクをクリックせず、検索結果やAI回答だけで満足してしまう現象をいいます。これは、従来のSEO対策では、サイトへの流入が減少してしまうことを意味します。
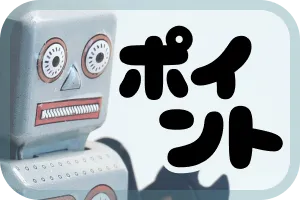 |
回答内に自社が引用されれば、露出や信頼の獲得につながり、企業のブランディング力の向上にも貢献できます。 |
デルフォイ的コスト
AIが不完全な知識や推測に基づいて回答を生成することで生じる「誤情報リスク」や「検証コスト」のことをいいます。
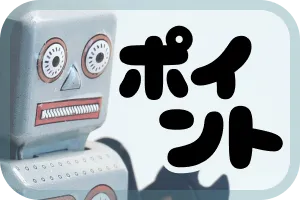 |
信頼できる一次情報を公式サイトで公開すれば、AIが引用する際の精度を高め、ユーザーの誤解を防げます。 |
クエリファンアウト
AIや検索エンジンが、1つの質問に対して、多数のサイトを同時に探索し、複数サイトから情報を組み合わせて回答を生成する仕組みです。つまり、採用される情報は、一つのWebサイトだけではなく、そのキーワードをきっかけに複数のWebサイトの情報が採用されるため、情報が整理された様々なWebサイトにチャンスがあります。
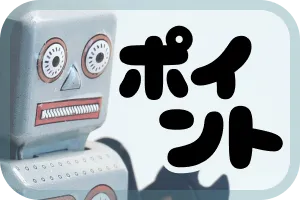 |
サイト構造の最適化、関連情報のまとめ方を工夫する必要があります。 |
クロールバジェット
検索エンジンが各Webサイトをクロールする際に割り当てるリソース量です。中~大規模サイトほど、このクロール予算を意識し、重要な情報にクロールされることを意識する必要があります。
例えば、「?page=2」「?page=3」といった大量のページャーURLが生成されると、このクロール予算の無駄遣いとなり、重要ページがクロールされないということになります。
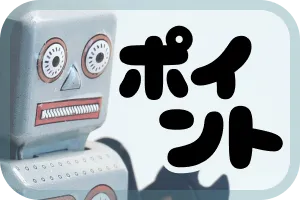 |
リダイレクトの整理、noindexの指定、サイトマップ最適化が上げられます。 |
RAG(Retrieval-Augmented Generation)
生成AIが外部データ検索を組み合わせて回答を生成する仕組みです。FAQやナレッジベースを公開すると、AIが情報源として引用されやすくなります。
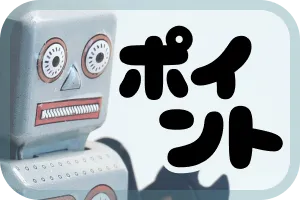 |
企業のオリジナルの公式情報をAIに拾わせるための情報設計を行うことで、その情報の有効性が高まります。 |
E-E-A-T
E-E-A-Tは「Experience」「Expertise」「Authoritativeness」「Trustworthiness」の頭文字で、SEO対策上でも重要といわれるGoogleが評価する「経験・専門性・権威性・信頼性」です。AI時代でも依然として重要な評価基準となっています。
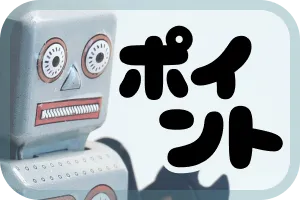 |
著者や監修者情報の明示したり、実績やオリジナル情報の公開で信頼性を高めることが重要です。 |
SEOとLLMOの関係

従来のSEOのゴールは「検索結果の上位に表示され、クリックを獲得すること」でしたが、LLMOのゴールは「検索エンジンやAIに正しく理解・引用されること」です。
ゼロクリックサーチが増加する中で、Web担当者はもはやクリック数の増減だけに一喜一憂するのではなく、自社コンテンツがAIに引用されるための信頼性・構造化を意識する必要があります。
現在のSEO対策におけるチューニングポイント

構造化データの徹底活用
FAQ、Product、Articleなどの構造化データを正しくマークアップすることで、検索エンジンやAIがコンテンツをより正確に理解できます。
特にクエリファンアウト(AIが一度に多くの情報源を探索するプロセス)を意識し、AIが関連情報を効率的に取得できる状態を整えることが重要です。
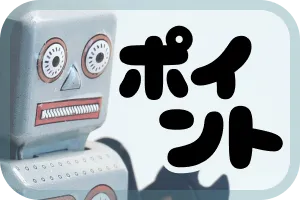 |
記事やサービス紹介ページを構造化データで補強し、AIに「引用されやすい形」で公開することが必須です。 |
コンテンツの信頼性強化
著者情報や監修者情報を明記することで、AIが誤情報を引用してしまうデルフォイ的コストを下げることができます。また、自社ならではの強みや専門性を明確に打ち出すことで、AI回答に採用される可能性を高められます。
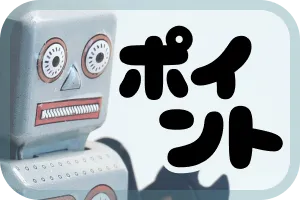 |
記事末尾やプロフィール欄に「執筆者・監修者の肩書・所属」を必ず記載し、信頼性を示すことが引用確率の向上につながります。 |
サイト構造の最適化
不要なURLや重複ページを放置すると、検索エンジンが巡回できるリソース(クロールバジェット)を浪費してしまい、重要なページが正しくクロールされなくなります。サイトマップや内部リンクを整理することで、検索エンジンが本当に重要なページに集中できる状態を作り出しましょう。
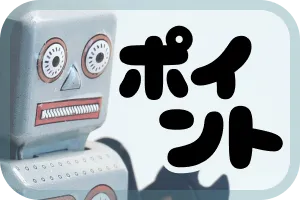 |
古いイベントページや重複コンテンツはnoindex・リダイレクトを徹底し、クローラーの無駄遣いを防ぎましょう。 |
コンテンツ設計の見直し
AIは「質問と回答形式」のコンテンツを引用する傾向があります。H2やH3見出しに質問文を取り入れることで、ゼロクリックサーチ対策に直結します。また、各ページ冒頭に「要約(3行程度)」を配置すると、AIが回答生成時に拾われやすくなります。
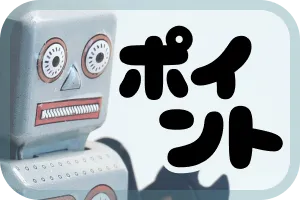 |
「◯◯とは?」「なぜ◯◯が重要か?」といったFAQ的な見出しを積極的に設計し、冒頭に結論要約を入れる習慣をつけましょう。 |
まとめ
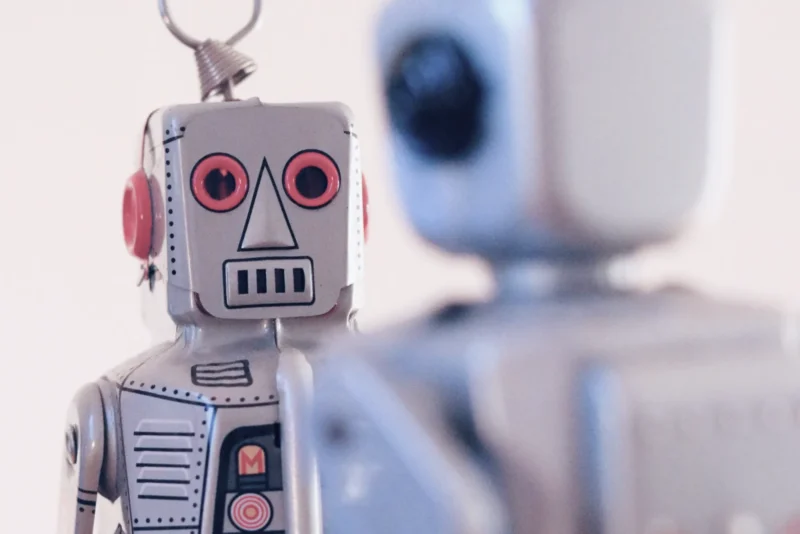
これからのSEOは「順位取り」だけを目的にするのではなく、AI最適化(LLMO)と一体で考えることが不可欠です。
下記ポイントをまとめます。
- ゼロクリックサーチの増加を前提に、「流入数」よりも「引用・認知」を重視する
- デルフォイ的コストを下げるために、信頼性の高い一次情報を公式サイトで公開する
- クエリファンアウトに備えて、サイト構造や内部リンクを整理し、情報が正しく拾われるようにする
- クロールバジェットを意識し、不要なURLを削除して重要ページを確実にクロールさせる
Web担当者は、従来のSEOノウハウを活かしつつ、AIに引用されるための整備を軸にした運用・改善にシフトしていくことが、これからのLLMO時代に求められる最大の課題です。
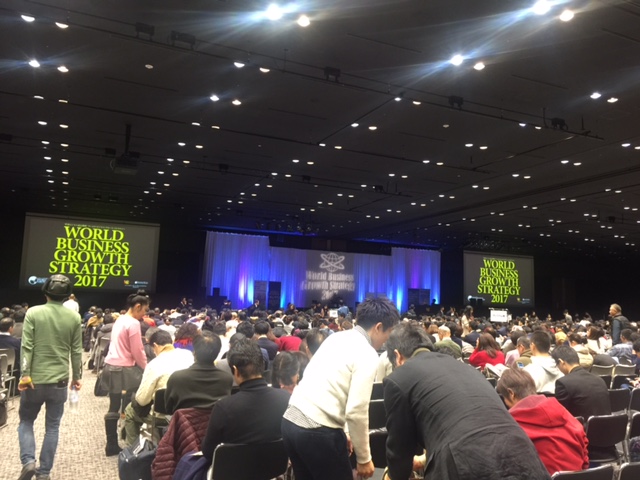
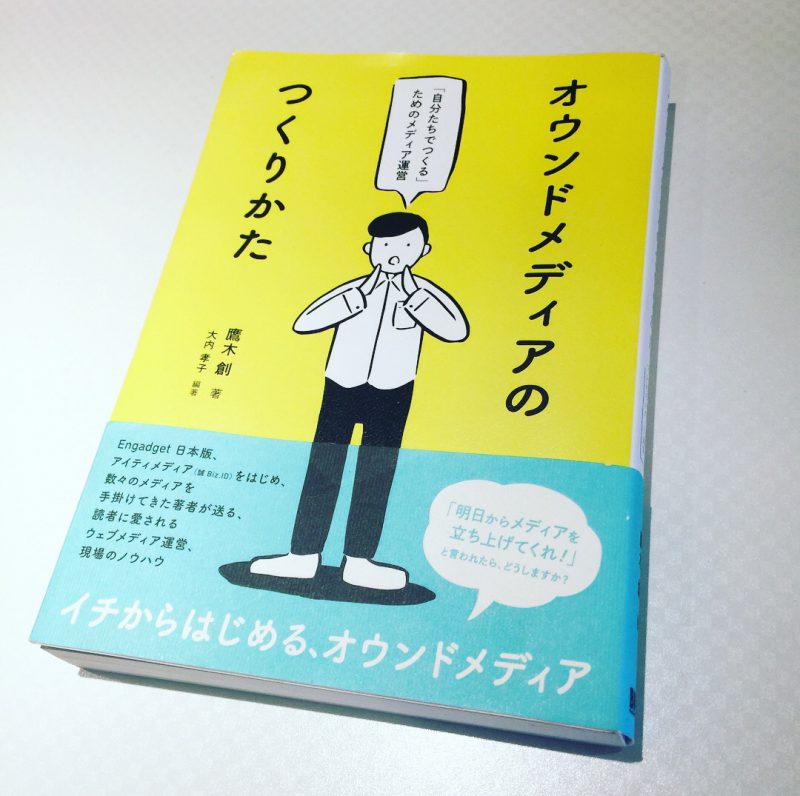

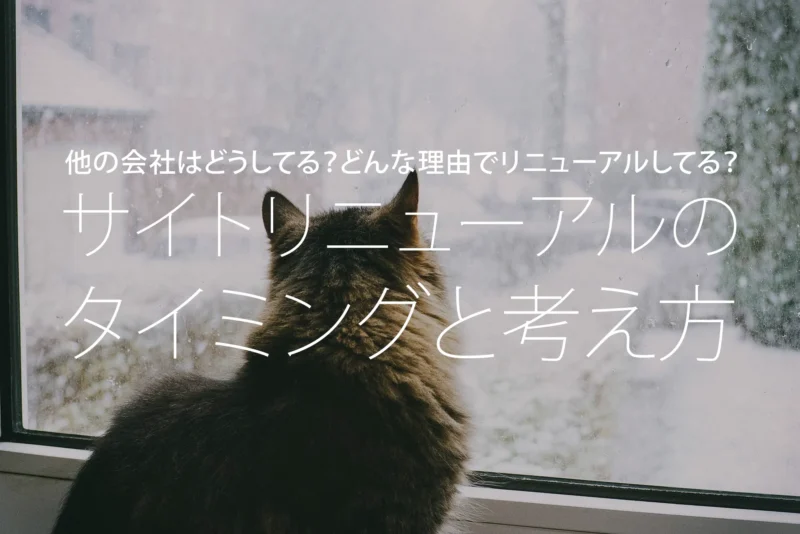
 お問い合わせ
お問い合わせ
